従業員満足度とは、企業におけるさまざまな要素に対する従業員の満足度を表す概念です。この記事では、従業員満足度について解説します。また、従業員満足度が重視されるようになった背景や、従業員満足度を構成する要素についても解説します。従業員満足度について知りたい人は参考にしてください。
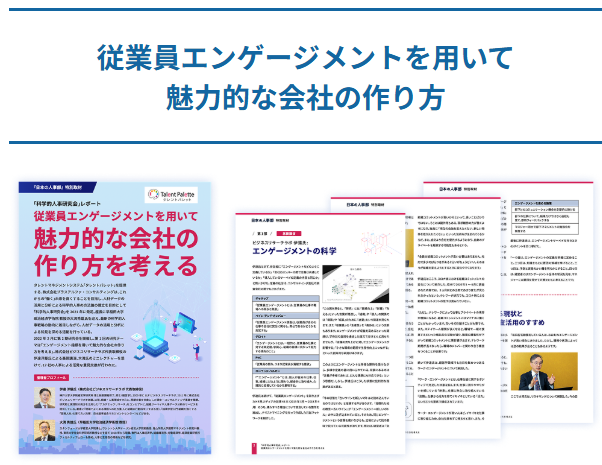
従業員満足度(ES)とは
従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)とは、文字通り従業員の満足度を表す指標です。頭文字を取って、ESと呼ばれることも少なくありません。主に、以下のような要素に関わる部分でどの程度満足しているかが判断されます。
- 労働環境
- 職務内容
- 人間関係
- 給与
- 福利厚生
成長を実感できたり、職場の人間関係が良好だったりすると、従業員満足度が向上しやすくなります。しかし、福利厚生が充実していなかったり、残業が多すぎたりすると、従業員満足度は低下しやすいでしょう。
従業員エンゲージメントとの違い
従業員満足度と似た言葉として挙げられるのが、従業員エンゲージメントです。従業員満足度は、企業に対する満足度の程度を表します。従業員エンゲージメントは、企業に対して自発的に貢献する姿勢や意欲のことを指します。従業員満足度の程度は企業への愛着を問いません。しかし、従業員エンゲージメントでは企業への愛着が重要な要素になります。
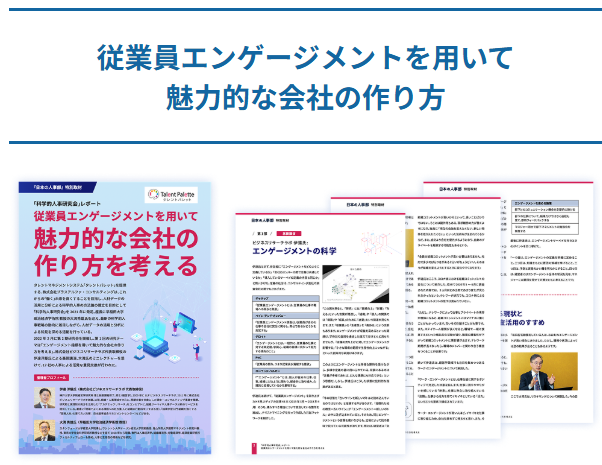
従業員満足度が重要視されるようになった背景
従業員満足度が重要視されるようになった背景には、人材に関わる環境の変化があります。転職のハードルが下がったことに加えて、副業が解禁された現代では、人材の流動性が高まっている状態です。
また、少子高齢化に伴い労働人口が減少し、人材の確保が難しくなっています。働き方改革の実施もあり、労働環境を整備して従業員満足度を高めることは重要な経営課題として認識されています。さらに、従業員満足度の程度は、企業における生産性に与える影響も小さくありません。顧客満足度の向上を目指す際にも関わるため、さまざまな部分で重視されます。
従業員満足度に関わる要素
従業員満足度に関わる要素は多岐にわたります。以下は、具体的な要素とそれぞれの詳細です。
企業理念・文化
企業理念や文化は、従業員満足度を左右する要素の1つです。企業理念や文化は、会社の目標やポリシーともいえます。また、従業員の価値観が企業と合致していると、働きやすいと感じる傾向にあります。
マネジメント
上司のマネジメントに対する納得感は、従業員満足度を左右する要素です。具体的には、適切に評価されていると感じることが重要です。また、上司が自身の仕事を把握していると感じると、従業員満足度は高くなる傾向にあります。
自身の仕事が周りに与える影響
自身の仕事が周りに与える影響も、従業員満足度に関わります。特に、会社の業績や社会への貢献に対する影響が重視されやすい傾向です。また、従業員が自身の能力やスキルを生かせていると感じると、従業員満足度は高まりやすくなります。
職場環境
職場環境と従業員自身のライフスタイルの相性は、従業員満足度に影響を与えます。主に、福利厚生の充実や就業規則の整備が重要なポイントです。さらに、ワーク・ライフ・バランスの実現も、従業員満足度の向上において重要になります。
職場における人間関係
職場における人間関係は、従業員満足度を左右する要素です。人間関係に不満や不安があると、従業員はストレスを感じやすくなります。また、モチベーションにも悪影響を与えるため、注意が必要です。
従業員満足度の高い職場の特徴
従業員の主体性や働きやすさなどは、職場環境によって左右されます。ここでは、従業員満足度の高い職場の特徴を解説します。
主体的に行動する
主体的に行動する従業員が多い職場は、満足度が高い傾向にあります。企業の理念や方針を理解したうえで、当事者意識をもって働く人が増えるためです。自分で考えて行動する従業員が増えると、組織の一体感も強まり、目標を達成しやすくなります。また、企業の労働生産性や顧客満足度の向上などにもつながります。
チーム内の活発なコミュニケーションが増える
チーム内のコミュニケーションが活発になると、議論やフォローなどが積極的に行われます。従業員間の情報共有がスムーズになり、チームの結束を強化することも可能です。業務効率向上によって評価も高まり、モチベーションの維持も期待できます。従業員が発言しやすい環境を整備すると、業績や成果などに影響するでしょう。
働きやすい環境が整備されている
従業員満足度は、職場環境の整備によって向上します。たとえば、デスク・チェアをはじめとした基本設備や福利厚生、適正な評価システムなどです。オンライン上の仕組み構築も必要なため、パソコンやネットワーク設備などの整備も大事です。効率よく作業をするための設備や仕組みに投資することで、ストレスが少ない満足度の高い職場を構築できます。
従業員満足度が低い会社の特徴
組織の体制や労働環境などが、従業員の働く意欲を低下させます。ここでは、従業員満足度が低い会社の特徴を解説します。
業務負担が大きい
業務負担の大きい職場環境は、従業員の満足度を低下させます。過度な仕事量を負担させると、心身ともに負担がかかるためです。また、長時間労働が続いたり、休みを取りにくかったりすると、ワークライフバランスの維持が困難です。生産性を向上させるには、適切な仕事量を割り振る必要があります。
変化を嫌う組織の文化や風土がある
変化を嫌う組織も、従業員の不満につながります。組織の規模が大きくなるほど、挑戦や失敗を恐れる文化や風土が生まれやすくなるでしょう。古い体質や慣習を変えない場合、職場内で価値観の不一致が生まれて、従業員の不満がたまります。上下関係や過度な成果主義など、従業員の意見が通らない職場は注意しましょう。
評価制度を整備していない
従業員が適切に評価されていないと感じる場合、組織に対して不満をもちやすくなります。たとえば、評価の基準が明確でなかったり、成果のみで評価したりするなどです。プロセスの評価も求められるため、公平公正な制度の構築が必要です。従業員が評価に不満を持つ場合、優秀な人材の流出するリスクも高まります。
従業員満足度の調査方法
従業員満足度を調査する際には、一定の手順を踏むことが大切です。ここからは、具体的な手順とそれぞれの詳細を解説します。
1.調査目的を明確にする
従業員満足度を調査する際には、調査の目的を明確にしましょう。調査には、従業員に時間を割いてもらう必要があります。しかし、目的なく実施すると時間が無駄になりかねず、従業員の不満を招く可能性があります。実施する際には、あらかじめ内容を社内に周知しておきましょう。
2.設問を策定する
調査の目的に合わせて設問を策定しましょう。管理職や役職の有無など、従業員の属性ごとに適切な設問構成を心掛けることが大切です。また、回答者が負担に感じることを避けるため、設問数が多くならないように注意しましょう。
3.調査を実施する
目的の設定や設問の策定などが終わったら、調査を実施しましょう。なお、調査目的によっては、社内の人間関係やプライベートに関する情報が含まれることもあります。そのため、結果の利用方法や共有範囲などをあらかじめ定めておくことが大切です。
4.結果を分析する
結果を分析する際には、課題や原因などを見極めることが大切です。さらに、さまざまな手法を組み合わせると、より効果的です。結果を分析する手法として、項目それぞれの合計や平均値を出す単純集計、設定した条件ごとに傾向の違いを見るクロス集計などが挙げられます。
5.結果を参考に対策を立てる
課題を可視化できたら、それらの課題の解決策や対策方法を検討しましょう。一般的な課題と解決策や対策方法は、以下のとおりです。
- 人事制度や勤務体系などの仕組みおよび運用の見直し
- 賃金や労働時間などの処遇条件の見直し
- 成長機会やキャリアビジョンの提示
- 福利厚生の見直し
課題の解決を目指す際には、準備を怠らないようにしましょう。なぜなら、関係各所の協力が必要な場合も珍しくないからです。
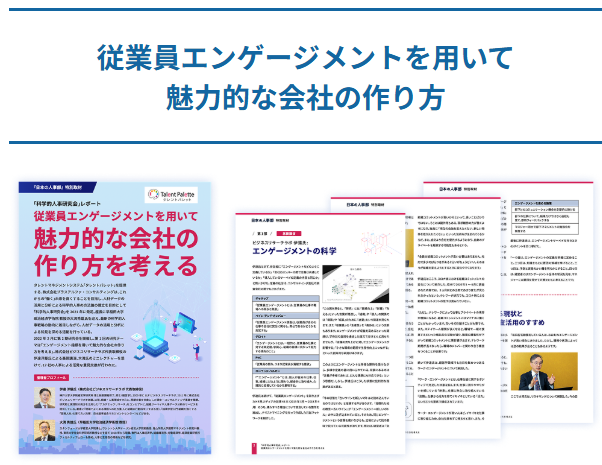
従業員満足度の調査項目
従業員満足度の調査項目は多岐にわたります。以下は、代表的な調査項目とそれぞれの詳細です。
仕事に対する満足度
仕事の負荷の程度や上司の対応への満足度を調査します。具体的には、自由記入の質問項目を用意したり、満足度を数値で示してもらったりしましょう。それらの結果を従業員の納得感や不満などのデータに落とし込みます。
処遇に対する満足度
処遇に対する満足度も、従業員満足度の代表的な調査項目です。特に、以下の項目について満足しているかを聞くと効果的です。
- 給与
- 人事評価
- 労働時間
- 休暇日数
上記の項目に対して納得感を得られている従業員は、従業員満足度が高い傾向にあります。
メンタルヘルスの状態
組織における人間関係や私生活に関するストレスについて調査しましょう。特に、人間関係に起因するストレスは、労働意欲の低下や離職にもつながりかねません。悪化を防ぐためには、早期に発見し適切にケアを行うことが大切です。
アンケートを作成する場合のポイント
アンケートを作成する際には、いくつかのポイントを意識しましょう。ここからは、具体的なポイントとそれぞれの詳細を解説します。
質問の数は適切な量にする
従業員満足度を調査するアンケートを作成する際は、質問の数を適切な量に調整することを意識しましょう。質問の数が多すぎると、回答者の集中力が削がれてしまい、いい加減な回答が増えかねないためです。しかし、質問の数が少なすぎても、項目間の相関関係を分析できなくなります。重複を避け、回答しやすい設問数を目指すことが大切です。
分かりやすい表現・内容を心がける
従業員満足度を調査するアンケートは、基本的に社内向けに実施されます。そのため、設問の内容を難しくしたり、堅苦しい表現にしたりする必要はありません。従業員にとって負担にならず、回答が制限されない表現や内容を心がけましょう。
回答者が特定されない作りにする
アンケートを作成する際は、回答者が特定されないよう配慮することが大切です。なぜなら、個人名が分かる状態では遠慮してしまい、不満や意見を伝えづらくなるためです。従業員の本音を聞き出すためにも、回答者が特定されない設計にしましょう。
経営層に合わせた内容にしない
ネガティブな回答を減らしたり、回答の方向性を誘導したりするような偏った内容にしないように注意しましょう。なぜなら、潜在的な課題が発見できず、アンケートの効果が薄れてしまうためです。
アンケートの結果次第では、制度を改善したり経営の方針を変えたりすることが求められます。しかし、制度の改善や経営の方針変更は、経営層にとって都合の悪い場合も多くあります。だからといって、経営層の都合がよくなるような内容にするべきではありません。
テンプレートを活用する
質問項目の作成は手間や負担がかかるため、テンプレートを活用しましょう。担当者のITスキルが不足している場合でも、効率よく作成できます。テンプレートの設問内容や回答形式などを統一することで、作成時間と工数の大幅な削減も可能です。
テンプレートはデータの管理や分析、アンケートの内容の改善などにも有効です。従業員の意見やアイデアを取り入れて、働きやすい環境の構築に役立てましょう。
従業員満足度アンケートの設問例
従業員満足度アンケートの設問は、二要因理論を参考にすることをおすすめします。二要因理論は、従業員の満足度に影響を与える要因が2種類で構成されるとする理論です。具体的には、満足に関わる動機付け要因と、不満足に関わる衛生要因が挙げられます。また、設問に対する回答形式は、以下の5段階の選択肢から選んでもらうことが一般的です。
とてもそう思う/そう思う/どちらでもない/そう思わない/全くそう思わない
従業員の基本情報
アンケート結果の分析や集計を行うために、従業員の基本情報が必要になります。具体的な設問例は以下のとおりです。
- 性別を教えてください
- 年齢を教えてください
- 所属部署や役職を教えてください
- 入社年を教えてください
動機付け要因
動機付け要因に関する設問には、以下のような内容が挙げられます。
| 業務内容について | ・現在の仕事はやりがいがある ・現在の仕事に対して興味や関心がある ・現在の仕事に価値や意義を感じている ・現在の仕事が社会や顧客の役に立っていると感じる ・仕事内容が自分の適性に合っていると感じる ・自分の考えで仕事を進めることができる |
| 評価や目標について | ・自分の仕事は適正な評価が得られている ・仕事を通じてスキルや能力を身に付けられる ・現在の仕事が自分の成長につながっている ・仕事を通じて達成したい目標がある |
衛生要因
衛生要因に関する設問として挙げられることは、以下のとおりです。
| 給与・待遇・福利厚生について | ・業務の内容や成果に対して給与が相応だと感じる ・労働時間が適切だと感じる ・希望する日数や日程で休暇を取得できている ・育児や介護を支援する制度が整っていると思う ・現在の福利厚生に満足している |
| 職場環境について | ・業務を円滑に遂行するために必要な設備や環境が整っている ・職場の人間関係は良好だと感じる ・職場のコミュニケーションや情報共有は円滑に行われている ・業務の合間のリフレッシュに利用できる場所や設備がある |
総合評価
総合評価に関する設問には、以下のような内容が挙げられます。
- 現在の職場で働いていることに満足している
- この会社で働いていることを誇りに思っている
- この会社で働いていることについて自信を持って話すことができる
- 今後もこの会社で働き続けたい
従業員満足度の調査ツールを活用するメリット
従業員満足度の調査は、ツールを活用することで効率を上げられます。ここでは、調査ツールを活用するメリットを解説します。
調査の手間を省ける
調査ツールを導入することで、従業員満足度の工数を大幅に削減できます。たとえば、項目の設定や設問の設計、アンケート作成などです。調査結果の回収や分析、改善策の提案など、調査の手間や負担の軽減につなげられます。
また、従業員情報を一元管理するタレントマネジメントにも有効です。スキル・経歴、評価情報などのデータを活用し、適材適所の人員配置や育成ができます。
課題の早期発見につながる
調査ツールによって、組織の課題や改善点などを発見しやすくなります。選択制の質問に答えるだけで、従業員の意識の把握ができるためです。秘匿性の高い調査によって、従業員の本音も引き出しやすくなるでしょう。評価制度や処遇、設備など、口に出せない不満が見つかることで、課題の発見と対策につなげられます。
モチベーションやエンゲージメントが向上する
調査ツールで得た回答を受けて、課題を改善することでモチベーションの向上につながります。ツールの導入や調査の実施などは、従業員を大切にする姿勢を示せるため、企業への帰属意識を高めます。企業全体で仕事に対する貢献意欲が高まり、エンゲージメント向上につなげることも可能です。
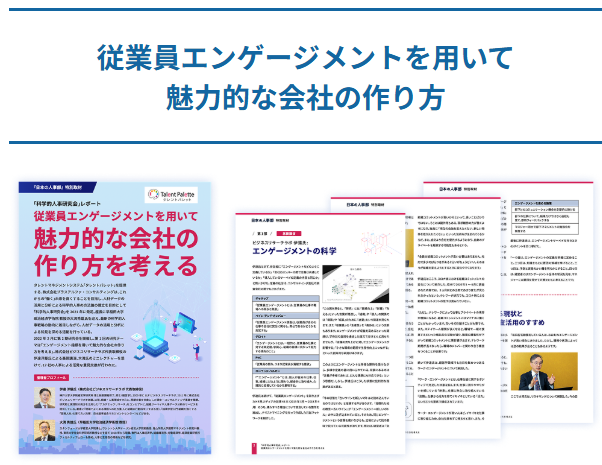
従業員満足度の調査ツールを活用する際の注意点
従業員満足度は、体制を構築して調査を継続する必要があります。ここでは、調査ツールを活用する際の注意点を解説します。
運用の体制を構築する
調査結果を活用するために、運用できる体制を構築しましょう。調査は目的ではなく手段なため、ツールでデータの集計をして、分析結果をもとに施策を実行・改善を続けることが必要です。
また、調査ツールの運用には、経営陣や管理職、現場の従業員が協力する体制が求められます。調査の目的や活用方法を共有すると、企業へのサポートを実感できるでしょう。改善策を実行することを示すことで、調査に対する協力を得やすくなります。
定期的な調査を継続する
従業員満足度は、継続して調査する必要があります。施策を実行する影響によって、従業員の変化を把握したり、ニーズを理解したりすることが大事です。調査結果をもとに改善を続けて、課題の対策に取り組まなければなりません。
改善策の検証を行い、満足度の変化を把握することも可能です。調査するごとに改善を続けると、従業員のモチベーションの向上が期待できます。適切な人事配置にも対応できるため、満足度の高い組織づくりにつなげられます。
従業員満足度が向上するメリット
従業員満足度が向上するメリットは多岐にわたります。以下は、代表的なメリットとそれぞれの詳細です。
生産性の向上
従業員満足度の向上により得られるメリットとして挙げられることは、生産性の向上です。従業員満足度が高い状態では、従業員のモチベーションや意欲も高まります。そのため、能動的・自律的に業務に取り組みやすくなります。また、不満やストレスが少ない状態なら、業務に集中しやすいでしょう。結果として、さらなる生産性の向上が期待できます。
コミュニケーションが円滑になる
従業員満足度が高いと、従業員同士の人間関係にもよい影響が出ることが利点です。コミュニケーションが円滑になると、業務の生産性の向上につながったり、成長意欲の向上を促せたりします。さらに、企業や組織におけるイノベーションも起こりやすいでしょう。新規事業の展開や新サービスの開発につながれば、企業の業績向上も期待できます。
離職率の低下
人手不足が問題となっている昨今では、従業員の離職率を下げて定着してもらうことが大切です。従業員満足度が高いと、従業員が長く働いてくれる可能性が高まります。働きやすい環境と判断されて優秀な人材も確保しやすいでしょう。
また、従業員満足度が向上すると、従業員の紹介による人材確保にもつながります。採用活動や離職に伴う引き継ぎなど、人材に関わるコストを抑えられることは大きなメリットです。
顧客満足度の向上
従業員満足度が向上すると、自社のサービスや商品の質も高まる傾向にあります。なぜなら、自社のサービスや商品への理解を深めたり、顧客に対する親身な対応を積極的にしたりするためです。また、提案や改善に関する取り組みに対しても積極的になります。そのため、顧客ニーズに合ったサービスや商品の提案にもつながります。顧客満足度を高めるためにも、従業員満足度の向上は重要です。
従業員満足度を高める方法
従業員満足度を高める方法はいくつかあります。代表的な方法とそれぞれの詳細は、以下のとおりです。
企業理念やビジョンの浸透
企業理念やビジョンを浸透させることで、企業に対する期待感や帰属意識を高めることができます。さらに、組織としての一体感が生まれ、従業員満足度の向上にもつながります。
浸透させる対象は、部署やチームといった単位に留めるべきではありません。個人の目標レベルまで企業理念やビジョンを落とし込むことが大切です。定期的に企業理念やビジョンを発信したり、1on1ミーティングを実施したりすると効果的です。
職場環境の整備・改善
職場環境の整備や改善は、従業員満足度の向上につながります。具体的な施策として、業務効率を向上させるシステムや制度の導入が挙げられます。
業務効率が上がれば、業務を円滑に進めたり、残業時間を減らしたりすることも可能です。従業員が働きやすいと感じると、従業員満足度が向上します。結果として、離職率の改善や生産性の向上も期待できます。
業務内容や配置の見直し
従業員満足度を向上させるには、業務内容や配置を見直すことも有効です。なぜなら、従業員が自身の特性に合っていたり、自身の能力を生かせたりする仕事ができると感じるようになるためです。従業員が持っているスキルを見定め、適切な業務内容を割り当てましょう。また、従業員の特性と業務内容が合っていない場合は、配置の見直しを検討する必要があります。
コミュニケーションの活性化
社内におけるコミュニケーションを活性化させると、従業員満足度が向上しやすくなります。風通しのよい環境は、従業員の心理的安全性が確保されやすいためです。
また、良好な人間関係を築くことは、業務効率を高めます。そのため、ストレスが軽減され、情報共有がスムーズになり、チーム全体のパフォーマンス向上に繋がります。
評価制度の適正化
従業員満足度を高めるためには、評価制度を適正化し、公平性の高い内容にすることが大切です。従業員が自身の評価に対して納得感を得られないと、不満を感じて従業員満足度が下がってしまいます。そのため、評価基準や昇給基準などを明確にし、複数人で評価を実施して客観性を担保しましょう。
また、評価結果の説明やフィードバックを適切に行うことで、評価に対する納得感を高めることができます。主観的な評価をしないように、評価者に対する教育も検討しましょう。
福利厚生の充実
福利厚生の充実は、従業員満足度の向上につながります。福利厚生とは、基本的な給与とは別に会社から提供されるものです。住宅手当や家賃補助、慶弔金や財形貯蓄制度などが代表的です。なお、福利厚生における支援は金銭的なものに限りません。たとえば、昼寝できる時間や場所を提供したり、法定外の特別休暇を設けたりするなども該当します。
まとめ
昨今の企業を取り巻く環境において、従業員満足度は重要な役割を果たします。しかし、従業員満足度は心理的なものであり、明確なデータや数値で測れるものではありません。そのため、適切な対応や取り組みを実施することが大切です。
タレントパレットは、人事に必要な機能がオールインワンで搭載されているタレントマネジメントシステムです。人事業務の効率化をはじめ、経営・人事戦略の意思決定の高度化や次世代人材の育成などの実現に貢献します。人事における課題を抱えている場合は、ぜひタレントパレットをご利用ください。

エンゲージメントの収集・分析で社員満足度向上や離職防止を実現|エンゲージメントを強化したいならタレントパレット|24年度シェアNo.1 タレントマネジメントシステム
「3分でわかる!タレントパレット」資料を今すぐ無料ダウンロード。3年連続No.1 タレントマネジメントシステム。継続率99.7%、様々な業界業種の先進企業が続々導入。人事評価の悩みを解決します。

